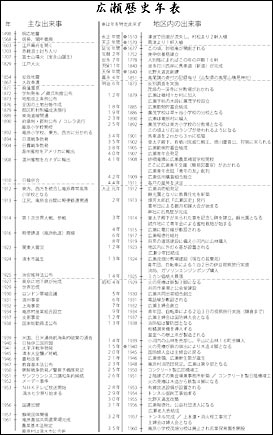広瀬の歴史
江戸時代以前
広瀬部落の発祥は古く明応7年(1498年)~永正7年(1510年)の間に最初の鍬入れがされたようです。1500年前後の日本の歴史はと言えば応仁の乱の直後、戦国時代が始まろうとしている時代です。あの織田信長でさえまだ生まれてはいません。
富士山も再三にわたり噴火を繰り返し、それにより駿河湾一帯に大地震、大津波が頻繁に起きていたようです。そのような中、清水市村松の住人であった私達の祖先2軒が地震による大津波で田畑を流失し、難を逃れて広瀬に入って来ました。そして、この数十年後の永禄11年(1568年)に、ほぼ天下統一を治めた信長が諸国の関所を撤廃していますが、撤廃に伴い清見関の役人をしていた1軒が職を失い広瀬に入り、前の2軒と合わせてこの3軒から広瀬の歴史は始まったとされています。そのため、広瀬のほとんどの家のお寺は遠く離れた清水市村松の海長寺、そして、興津の清見寺になっています。また、姓も殆ど全戸が「杉山」姓です。
江戸時代
当時広瀬に入るには波多打川沿いの山道を越えてくるしかなかったと思われますが、波多打川には途中「ドウドメキ」と呼ばれていた川の狭まった谷があり、そこを越えた所に広がる広い瀬を見て広瀬の地名が付いたと思われます。

この後の資料があまり残っていないため江戸末期までの事はよく分かっていません。江戸末期の古文書には他部落との境界争いの記録が残っていますが、これには韮山代官であった有名な江川太郎左エ衛門の名も出てきます。
この時代までは昔からの山越えの山道を歩くしかなかったようです。しかし、道路の必要を感じた部落民の努力により、天保11年(1840年)に波多打川沿いに新道(馬車道)が完成しています。戸数十数戸の人員で農作業の合間に時間を作り、何年もかけての大変な工事だったと思われます。
明治時代
その後、明治時代になると広瀬に入ってくる道路だけでなく産業の発展の為にも村内の道路も又拡張に迫られてきます。何回となく道路工事は行われていますが川沿いの狭い道ですから災害のたびに崩壊し、その復旧にかかる維持費もかなりの額にのぼったようです。
大正の初期にトンネルを掘る計画が進められたようですが、資金面を考えると二十数戸の部落では不可能に近く、そこで将来のために資金作りをして時期の到来を待つことにしました。
トンネル工事
まず、当時の共有地に生えている松を伐採しそこに植林し、松材売却代金で六町歩の山林を一万円で買いました。そしてこれを補植、下刈り管理し20年後に2万円で売却、そしてそれを元手に16町歩の山林を9千円弱で買い取りトンネル工事が出来るようになる時代をじっと待っていました。
実際にトンネル工事が始まったのは昭和29年になってからでした。この年の5月10日に起工式が行われています。足かけ4年の歳月をかけ、完成は昭和32年で8月17日に竣工式が行われました。これで、50年近く2世代にわたり、村民の夢であったトンネルができ、災害時にも壊れない道路がようやく完成しました。
また、この工事は補助事業でしたが、地元負担分1400万円は先人達がこの時のために買って維持管理していた山林を売却しこれにあてました。これがなんと買い取り時の1500倍にもなる1400万円で売れ、結局全てをこれでまかなえたといいます。
今の時代とかく結果を急ぎ短期で考えてしまいがちですが、何十年も先の子孫の為に、今何かをしておく事も大事な事のようです。
地区内の道路整備
この時期トンネル工事と平行して、村内の道路の拡幅工事も積極的に行われました。当時は広瀬の主産業であるミカン栽培も景気のいい時代で、収量も急激に増えていったため、大型車両の通れる道がどうしても必要でした。
このように、近代における広瀬の歴史は道路の歴史とも言えるくらい、それほどまでに広い道路、大雨でも壊れない安全な道路を願っていました。これは、全国どこの山間地でも同じようなものだと思います。生活している村民にとっては子供でも安心して通れる道は夢にまで見る道路だった事でしょう。
続きへ ▲